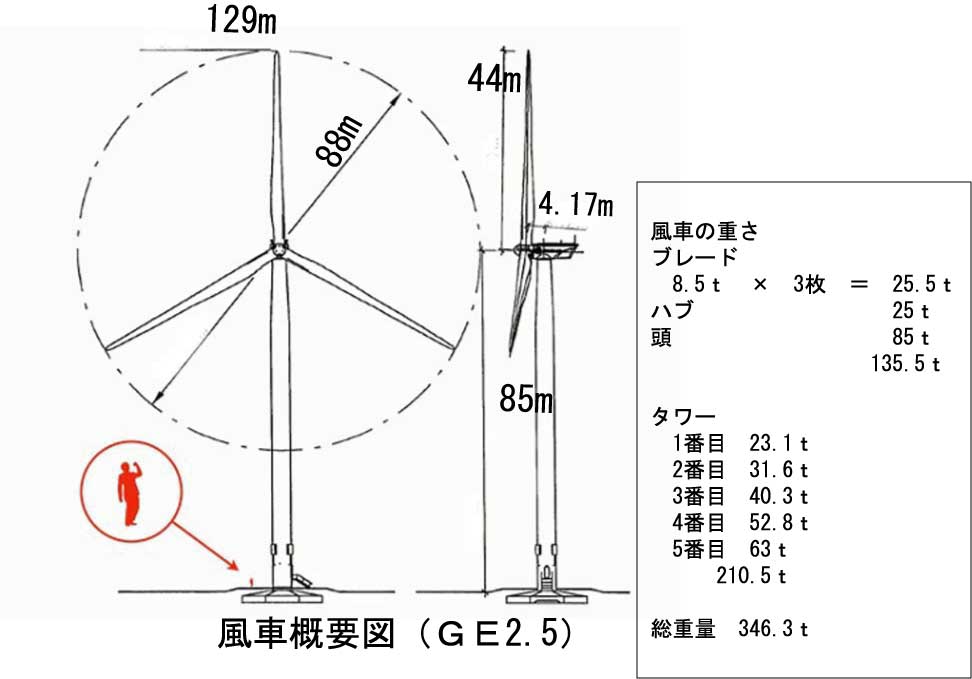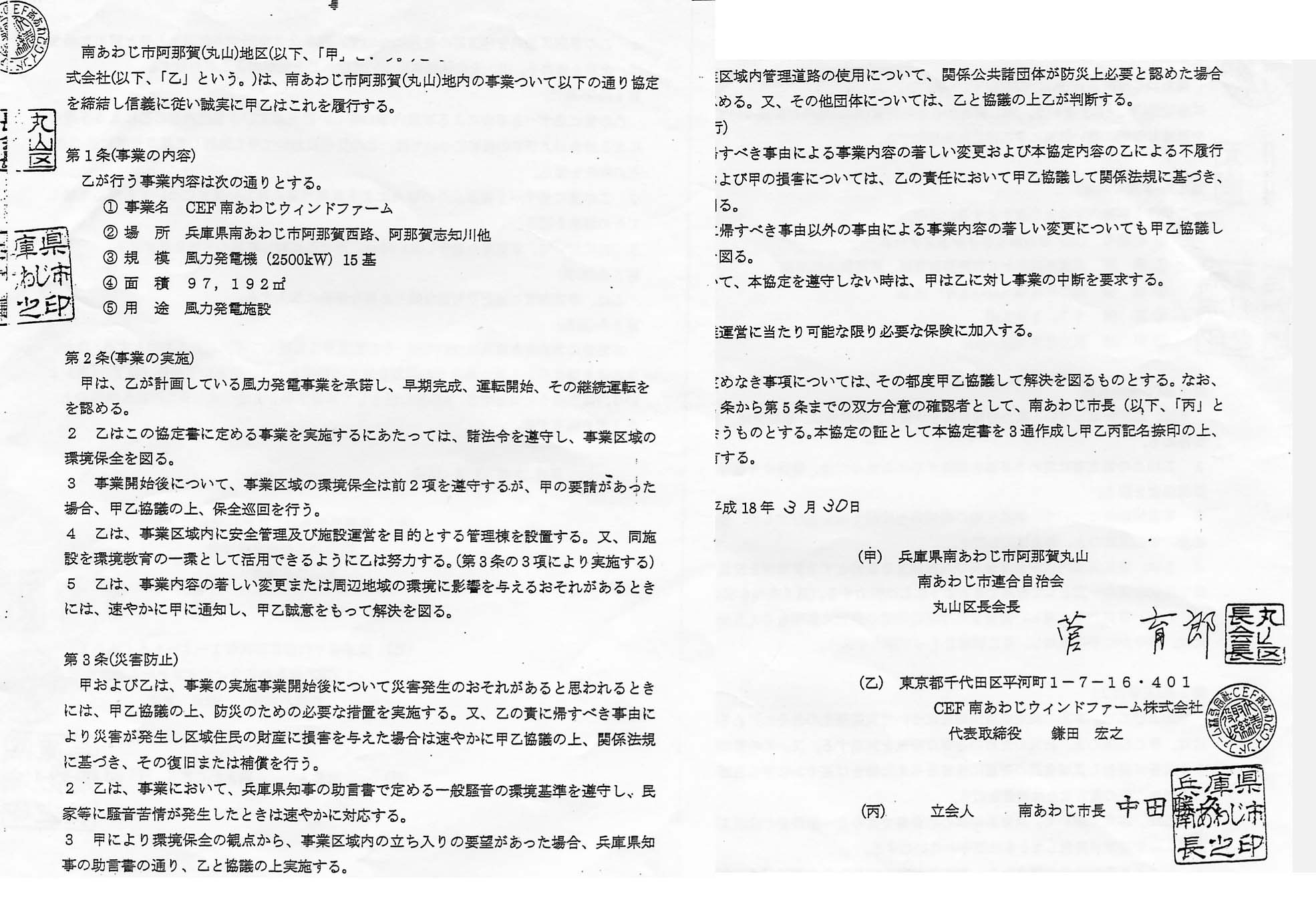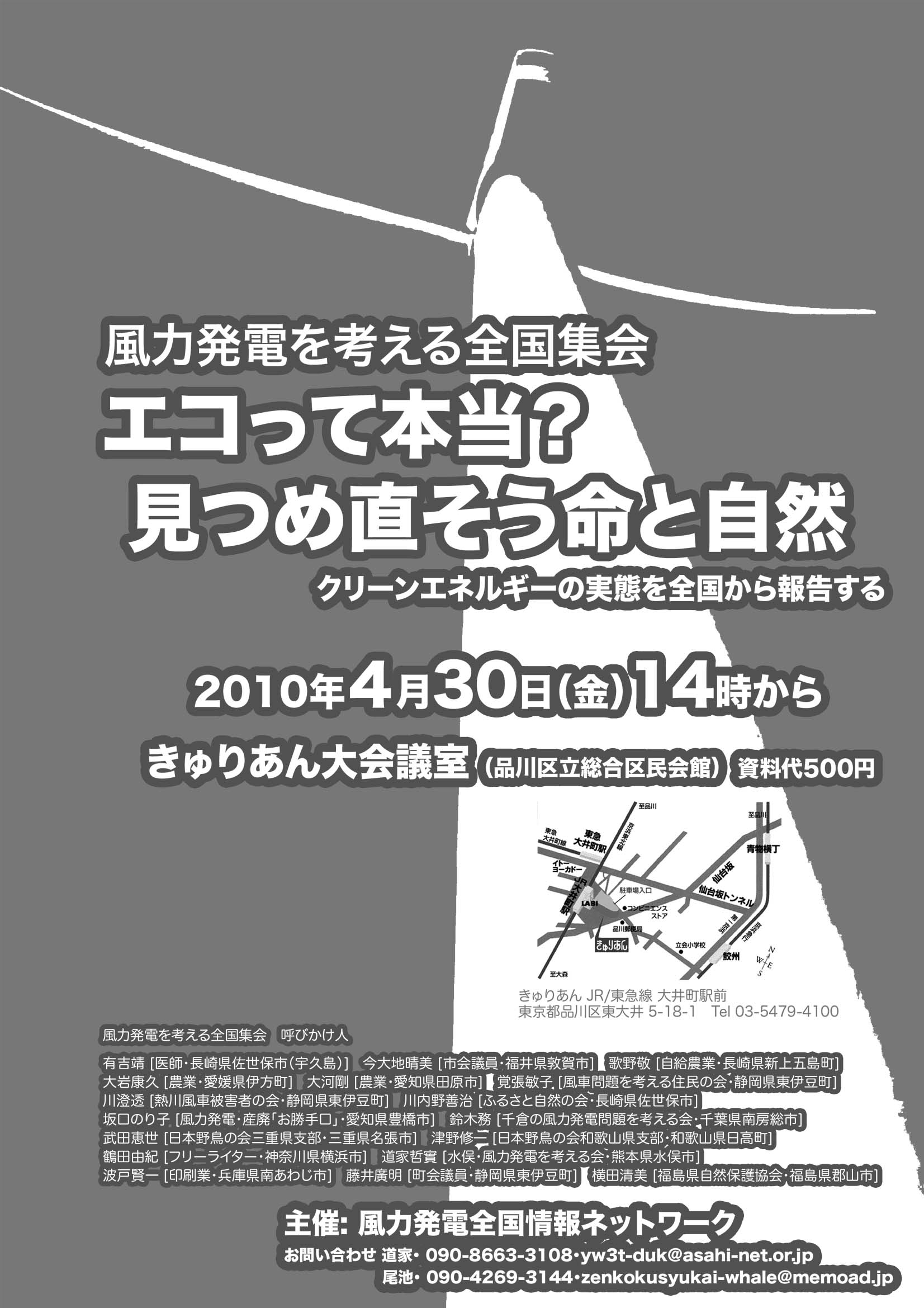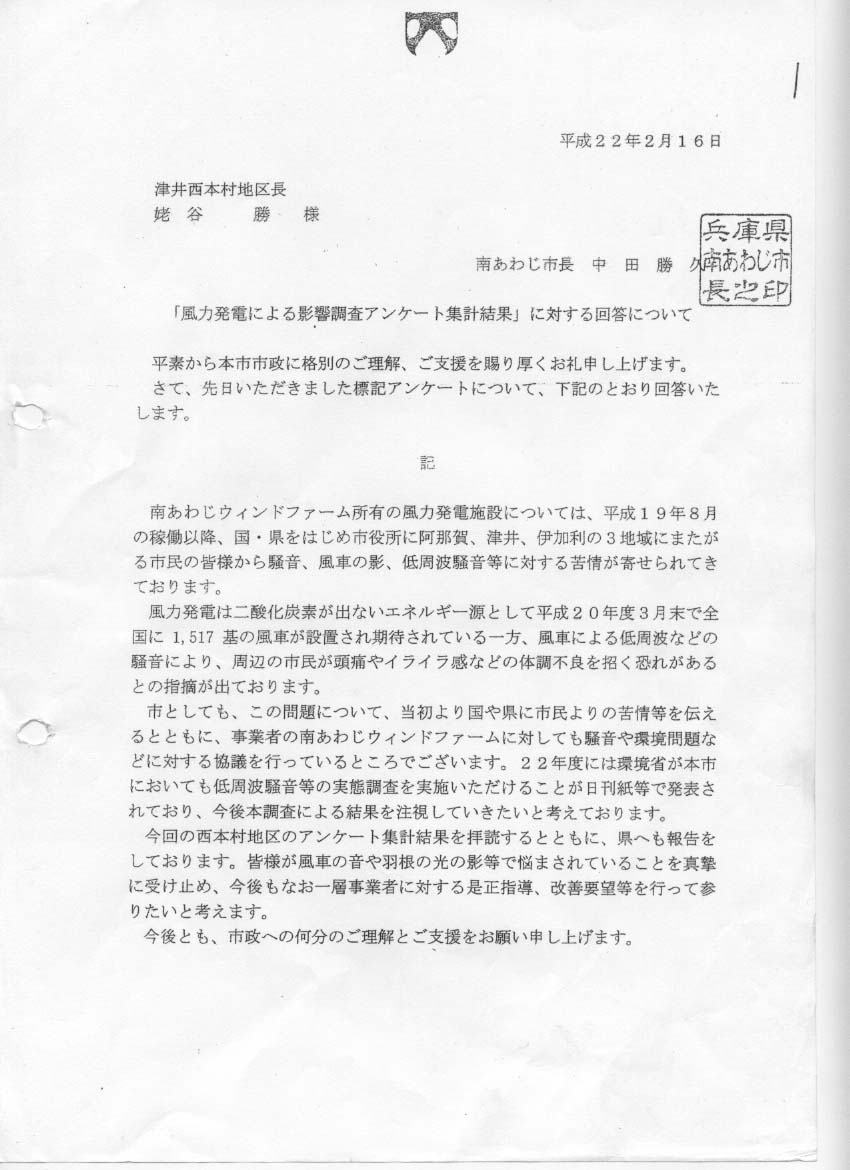| 風力発電に関する議論 |
| 風力発電に関する議論Ⅱ |
 風力で翼(ブレード)を回転させ、連結したタービンを回し発電する方法。 風力で翼(ブレード)を回転させ、連結したタービンを回し発電する方法。風力発電は、大気の流動をエネルギーに変換する為、基本的には環境負荷のない発電方法とされている。 ただし、エネルギー確保は大気流動により増減し、発電機自体の騒音も存在し、大型の電力供給を発生させる物は気軽に設置できる物では無い。 発生するエネルギー総量は2011年時点では効率が良い物では無い。 日本の風力発電がダーティな発電であるという意味 (鐸木能光[たくきよしみつ] 福島市出身の作家) http://takuki.com/dsk/005.htm この中で鐸木さんは 「風まかせで発電したりしなかったりする、その気まぐれな電力を買う義務を法的に負わされた電力会社としては、仕方なく買うが、その電気はもともと別の手段(火力や原子力、水力)で発電していた電気と「まぜて」使うことになる。風力発電所が発電しているときはその電気を100%使って、その分、大型火力や 原子力をこまめに止めたり出力を落とすということは無理なので、他の発電施設の稼働時間や消費しているエネルギーが大きく減るわけではない。 原子力はもともと臨界状態になったら出力調整は極力したくないシステム(出力調整棒の抜き差しは危険だから)。普通は一回発電状態になったら、次の定期点検で炉を止めるまではフル稼働で動き続ける。 火力も、大規模発電所ほどこまめに出力調整することは難しい。「何月何日の何時から何時までは風力から○○kw来ます」と分かっていれば、その時間をスケジュールに入れて出力を落とすこともできるだろうが、そうはいかない。まさに風次第なのだから、発電能力がいちばん余っている深夜の時間帯に風力発電から大量の電気を買わなければならないという不条理が日常的に起きる。 深夜帯は、ただでさえ原発から生じる余剰電力を消費するために揚水発電所などを稼働させている。そこに追い打ちをかけるように気まぐれな風力発電所から電気が送られてきても迷惑なだけだ。 このように、常に予想使用量を上回る電力を準備していなければならない電力供給システム全体にとって、いつなんどきどれくらいの電力が得られるのかまったく予想が立たない風力発電は、ただのお荷物でしかない。・・・・・・・・・・・・」 最初は悪意を持って風力発電を進めた人はいなかったであろう。 化石燃料を使わない自然エネルギーを期待しただ、問題点が沢山あることがわかってきた。 ところが役人の悪いところは、そこでUターンすることをしないから面倒なことになっている。 エネルギー政策は国策でもあることから、手厚い、ノーチェックの補助金政策、優遇政策が更にやっかいなものになっている。 |
| バードストライク |
 バードストライク(bird strike)とは鳥が構造物に衝突する事故をいう。 バードストライク(bird strike)とは鳥が構造物に衝突する事故をいう。主に航空機と鳥が衝突する事例を指すことが多い。この他、鉄道、自動車、風力発電の風力原動機、送電線や送電鉄塔、ビル、灯台などにおいても起きている。 ( Wikipedia) 稼働する風車に鳥類が激突死する「バード・クラッシュ(バードストライク)」が問題になっている。 生態系を考慮に含めた、風車を渡り鳥の通り道を避けて設置する等の工夫が必要である。 風力発電機の反対派が特に主張しているため、風力発電機がきわだって報道されている。 兵庫県では段ヶ峰ウィンドファーム ~イヌワシ生息地に計画された風力発電施設~ 事業者が開発許認可申請を取り下げ、建設は中止となりました http://www.d1.dion.ne.jp/~akaki_ch/dangamine.html この自然豊かな段ヶ峰での風力発電施設建設は、イヌワシVS風力発電の問題ではありません。また、風力発電が善か悪かというものでもありません。 問題なのは、 1)法律で保護されている希少野生動物が生息する自然環境を大きく破壊することが目に見えており、さらには関連工事に起因する土砂崩れなどが懸念される場所に風力発電施設を建設しても良いのか、 2)そこまでして建設する風車が、多雪山岳地帯の過酷な環境下で適切に稼動し管理されて、本当に二酸化炭素排出削減に貢献するのか、 3)長期的に見て、本当に地元市民や国民の利益になる計画なのかということです。 2006年11月、事業者側(CEF)が「イヌワシ餌付け計画」を朝来市議会および兵庫県環境影響評価審査会に提出していることが明らかとなりました。この計画は同年4月頃には既に提出されていたものと見られています。 風車からイヌワシを遠ざけ、また風車建設で失われるイヌワシの狩場の代償として考えられた計画。 計画内容は猛禽を熟知する者が関わったとは考えられない稚拙なもので、猛禽の専門家は計画を批判しています。 事業者は餌付け計画をもって「イヌワシとの共存」を謳っていたが、そもそも計画地を除いて周辺に生息適地が無い状況で、風車建設とイヌワシの生存を両立させようとすることが無理な話です。 その程度の事業者クリーエエナジーファクトリ(CEF)が全国で風力発電事業を展開しています。 わが南あわじ市にも(2500kw)の風車が15基建設された。 |
| CEF南あわじウインドファーム |
 海抜約120~230m、南北約4kmの丘陵地に、高さ約85mの風車を15基が建設されました。 海抜約120~230m、南北約4kmの丘陵地に、高さ約85mの風車を15基が建設されました。北海道根室市の発電事業者「クリーンエナジーファクトリー(鎌田宏之社長)」による現地法人「CEF南あわじウィンドファーム」として事業を行っている。 建設に際しては、大規模な開発であることから兵庫県の環境影響評価(環境アセスメント法)の対象でもあり、法律を守ることが絶対の条件でした。 地域住民の合意が必要である筈なのに、住民との十分な話し合いも行われないまま、建設許可が出され、工事が完成して稼動しています。 [兵庫県]環境影響評価概要書作成基準 環境影響評価準備書作成基準及び環境影響評価書作成基準 http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/eia/sakuseikjn.html 兵庫県知事は・・・ 事業実施区域の周辺地域は、豊かな自然環境の中で生活が営まれている地域であることから、兵庫県知事から「自然環境や生活環境に影響を与えないように、環境監視調査結果については、適宜公表すること。 予測できない事項や環境に著しい影響が生じるおそれがある場合には、関係機関と協議し、必要な措置を講じること。また、事業の実施に当たっては、事前に地域住民に十分説明を行うとともに、要望・苦情等に適切に対処いなさい。」としている。 私たちは、文明社会に住んでいる以上、電気を使わずに生きていくことは難しい。 電力を得るためには、火力、水力、原子力などありますが、その中では太陽光発電などと並んでクリーンエネルギーであるといわれている風力発電もある。 地球の温暖化議論の中で再生可能エネルギーとかクリーンエネルギーなどといわれている電源をよく考えると、電力事業と補助金問題が見えてくる。 そこには政治家も見え隠れする。 僻地の人間だけが犠牲になっても良い理屈はない筈だ。 |
| 環境影響評価 |
| 南あわじWFの何が問題か |
| 風力発電を考える全国集会・呼びかけ |
| 風力発電全国情報ネットワーク 東京宣言2010 |
| 住民の苦しみもスルーか? |
ホーム