| HOME | 遠くへ行きたい | |画像投稿| |
| 知らない町を 歩いてみたい どこか遠くへ 行きたい 知らない海を 眺めていたい どこか遠くへ行きたい (ジェリー藤尾の遠くへ行きたい) 人が未来へ歩んでいくためには、前を向き 自分の正面を照らす光を目指し進まなくてはならない。 人生という名の「旅」はこれからも続く ※駄文をならべていますが、コメント歓迎です。(^_^) |
 |
|
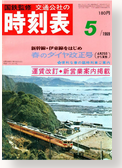 |
|
|
 |
|
 |
|
| [管理] |
CGI-design
| HOME | 遠くへ行きたい | |画像投稿| |
| 知らない町を 歩いてみたい どこか遠くへ 行きたい 知らない海を 眺めていたい どこか遠くへ行きたい (ジェリー藤尾の遠くへ行きたい) 人が未来へ歩んでいくためには、前を向き 自分の正面を照らす光を目指し進まなくてはならない。 人生という名の「旅」はこれからも続く ※駄文をならべていますが、コメント歓迎です。(^_^) |
 |
|
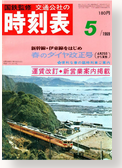 |
|
|
 |
|
 |
|
| [管理] |
CGI-design